※アフィリエイト広告を利用しています
こんにちは、こんばんは、えるです
歳を取るに連れて、今まで通りの考え生き方では難しいのではと日々感じるなかで
中年ならではの悩みを扱った本
「中年危機」著:河合隼雄
をご紹介
MEMO
・中年目前の人におすすめ
・考えてもうまく答えがでず、新たな視点を知りたい人におすすめ
作品概要

本:「中年危機」(朝日文庫)
著者:河合隼雄
発売:2020年9月7日
解説
中年ほど心の危機をはらんだ季節はない──
日本文学の名作12編を読み解き、職場での地位、浮気、子どもの教育、老いへの不安に戸惑い、人生の大切な転換点を体験する中年の心の深層をさぐる、心理療法家ならではの「中年論」
中年を楽しく生きるために読んでみた
オードリー若林さんの「ナナメの夕暮れ」で著書のことに記載があったので
興味が湧いて手にとってみた
めちゃくちゃ難しい
歳は中年だが、中身は中年に至っていないのだ
一昔の前の中年の人は、これを理解していたのかなと思うと理解できないのはなぜなんだろう
この著書は、章ごとにひとつの文学作品を取り上げて、中年の問題に焦点を当てている
そもそもこの文学書を通過していないことも、問題のように感じた
内容
以下の内容で構成されている
「目次」
・はじめに
第1章 人生の4季 夏目漱石「門」
・崖の下の家
・潜在するX
・父母未生以前
・春来りなば
第2章 40の惑い 山田太一「異人たちとの夏」
・屋根を歩く
・訪れる女性
・故郷への回帰
・多層的な現実
・どうかしていたのか?
第3章 入口に立つ 広津和郎「神経病時代」
・押し寄せる憂うつ
・さらば青年期
・暴力の意識化
・新しい課題
第4章 心の傷を癒やす 大江健三郎
・現代人共通の苦悩
・センチメンタリズム
・十字架のつなぎ目
・アレとソレ
第5章 砂の眼 安部公房「砂の女」
・みちしるべ
・たましいの掃除
・真の前衛とは
・よりどころ
第6章 エロスの行方 円地文子「妖」
・合一への欲求
・夫婦の行きちがい
・「坂」への恋
・深夜の来訪者
第7章 男性のエロス 中村真一郎「恋の泉」
・現代男性のエロス
・二人の女性への愛
・肉の俗説への疑問
・「事件」と「体験」の違い
第8章 2つの太陽 佐藤愛子「凪の光景」
・朝日と夕日
・春の訪れ
・家族コンストレーション
・勝負はこれから
第9章 母なる遊女 谷崎潤一郎「蘆刈」
・トポスと「私」
・慈母に抱かれて
・円環の時
・現実の多層性
第10章 ワイルドネス 本間洋平「家族ゲーム」
・子どもの「問題」
・過保護と暴力
・家族のバランス
・沈んでこそみつかるもの
第11章 夫婦の転生 志賀直哉「転生」
・ロマンチックラブ
・狐か鴛鴦か
・合一から裏切りへ
・死の体験
第12章 自己実現の王道 夏目漱石「道草」
・思いがけないこと
・過去現在未来
・視点の移動
片付かない人生
あとがき
巻末エッセイ 養老孟司
解説 河合俊雄
そもそも著者:河合隼雄とは・・・
河合隼雄
臨床心理学者、ユング派分析家
著者は日本人で始めてユング派分析家の資格を得る。その際、C・A・マイヤー (Carl Alfred Meier) に師事した
ユング派分析家とは
スイスの精神分析医カール・グスタフ・ユングが創始した分析心理学に基づいて、心理療法を行う専門家のことを指します
ユング派分析家の資格とは
心理資格「ユング派分析家国際資格」ISAP(国際分析心理学研究所、本拠地スイス)が認定する資格
2023年時点では、わずか51名が所持している

心理学者が中年の悩みを分析した本
専門的な分野の方が、文学を通して中年期に悩む事柄を、文学を通して説明していく
現代に生きる中年にとって、大きい問題を生ぜしめるのは、平均寿命が長くなったこと
人生50年と言われた一昔前のような人生ではなく
平均寿命が長くなったことで80歳くらいまで、生きることになる
すると今まで通りの考え方で、生きるのは難しい
長い人生のなかで、老年になりそれまでの生き方とは異なる人生観や価値観をもって生きることが必要になる
それは、ユングの言う「人生の後半」の生き方を自分なりに見出さねばならず
それを行うには、中年からの心がけが大切である
上記のような根源的な考えを基にして
中年で直面する、今までの自身の経験だけではなく、新しい方法を見出す必要がある
ではどういう考えをすればいいのか、というのが文学を通して説明されていく
文学を通して、説明するためなんの文学を利用するのかが大事になると思うが
著者の場合、自身が読んでいて自分が心動かされた文学を利用されている
人によっては、とても読みづらいかもしれない
個人的には文学を通すことで、とても読みやすく理解しやすくなっているように感じる
1回読んで理解するというよりは、数年に一度読み直すことで感じ方が変わるだろう本である
正直端的に、要約してまとめてご紹介するのは難しい
専門家の方が、要約したものがこの本になるので、それを素人が要約すると意味が変わってしまう
扱う内容が、章毎に変わるので尚難しい
1つなるほどな~と感じた箇所について
【第1章 人生の4季 夏目漱石「門」】
・潜在するX
夫婦の争いをするときの思考パターンを説明されている
多くの夫婦は、原因ー結果という思考パターンを武器に争いを行う
夫が酒を飲みすぎる「から」、家計を圧迫し過程が暗くなってくる
「だから」子どもが非行になど走るのだと、妻は説明する
あるいは、夫が妻に対して、お前があちこち出かけてゆく「から」、子どもはやる気を無くし不登校になってしまう、と非難する
確かに、論理的に道筋が通っていて、夫の飲酒や妻の外出が、悪の「原因」であるように思われる
おそらく相手の方が「原因」であるという論理が展開されるだろう
自分は悪くないが相手が悪い、とお互いに言いたいのである
問題は原因ー結果などと、論理的、継時的な道筋によっては把握出来ないところに、その本質があることなのだ
というのが、心に残った
個人的な解釈だが、お互いがお互いの視点で私は悪くなく、相手が悪いとする
確かに、原因ー結果という思考パターンで、解決したことで溝が生まれてしまうこともある
とても読んでいて、面白かった
おーなるほどな~とこういう考え方もできるのだと、納得してしまう
このように、いろいろな視点を、文学を通して説明されているので
とっつきにくい心理学者の本を読むより、まだわかりやすい
そろそろ中年?ぐらいになり、いままでの考えが通じないのでは?
と感じた際には一度、読んでみると新たな視点を気づかせてくれるかもしれない
以上です
購入する際には、以下から
最後まで読んでありがとうございます。
Xやコメントで「中年危機」を読んでどう感じたか、どういう部分が参考になったか等々感想を頂けると、更新する励みになります。
その他にも、とてもおもしろい考えにふれることができる
「オードリー若林正恭のエッセイ「ナナメの夕暮れ」の魅力を紹介」の記事や
星野源さん著書エッセイ「いのちの車窓から」の魅力を紹介しております
おしまい~~~~~




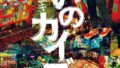
コメントを残す